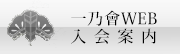こんぴら歌舞伎にご出演中の松也さんに、こんぴらよもやま話をご紹介頂きます。
毎年四月に開催される「四国こんぴら歌舞伎大芝居」に、6年振りに出演なさっておられます
(松也)
久しぶりで懐かしいですねえ(笑)。毎年公演初日の前日に役者が「お練り(人力車に乗ってのパレード)」をする習慣があるのですが、お練りをさせて頂くと気合が入りますね。今回も地元の皆さんに歓迎される喜びを全身で体験出来て、気合が入りました。前回(2008年:23才)は子役以来のこんぴらで、大人になって初めてでしたから、何事も初めてという感覚でした。今回は「戻って来た」ですね。お練りで「お帰りなさい!」との声をかけても頂いて、田舎に帰って来た様な、おばあちゃんちに帰って来た様な、そんな気分になりました(笑)。
初出演(1992年:7才)の思い出をご紹介ください
(松也)
今回ご一緒の、市川染五郎さんも市川高麗蔵(こまぞう)さんもいらしてました。「太刀盗人(たちぬすびと)」という舞踊劇で、うちの父がすっぱの九郎兵衛役で、染五郎さんが田舎者万兵衛の役をなさっていました。僕は「重の井の子別れ(しげのいのこわかれ)」で、腰元役でいらした高麗蔵さんと共演しました。三回という数少ない僕のこんぴら出演のうち、二度染五郎さんと高麗蔵さんとご一緒というのは、ご縁を感じますね。
僕は「重の井の子別れ」の三吉役をつとめましたが、肺炎で病院に通いながらの舞台でした。肺炎になって、声は出ていたけれどとにかく身体の調子が悪くて、終演後タクシーで丸亀か何処かの病院へ行って点滴を一時間くらい打っての宿に戻る、という生活をほぼ毎日続けていました。舞台はまあなんとかつとめました。僕の担当の黒衣さんがビニール袋を持っていらして、「もし駄目だと思った時は、ここに吐きなさい」と構えていてくださいました。そんな必要はなかったですけれど、周囲は気が気ではなかったでしょう。舞台を休みたいとは言いませんでした。つらかったけれど、やらざるを得ないとわかっていました。舞台に出るのはいやではなかったです。舞台に上がってしまえば演技に集中して、気分が悪いのを忘れられましたから。
前回の二度目のこんぴらでは、坊主頭になるというドラマ(?)がありました
(松也)
あ~、そういう事がありましたね(笑)。四国に来る前に、既にかなり短い、ほぼ坊主に近いくらいの短さに切っていたのですが、どうもそれがあんまり気に入らなくて、「もういっその事、坊主にしてしまえ!」と決心したのです。人生で僕は一度も坊主にした事がなかったので、ただの勢いでやってみました。市川海老蔵さんにバリカンをお借りして、尾上右近君に剃ってもらって坊主にしました。それで気が済みました。もう二度としません(苦笑)。
どうしてもうしないんですか?
(松也)
いやもう、あまりに不評だったもので・・・(派手に苦笑)。手入れが楽なのはよっくわかりましたけれどね(笑)。似合っていたら、ずっと坊主にしていたかもしれませんね。ホントに楽ですから!
こんぴらでの公演は、仲間同士の絆を深める絶好の機会であると伺っています
(松也)
前回の時はしょっちゅう皆でボードゲームしていましたね。ついこの間も、「ひと部屋に集まって遊ぶので、いらっしゃいませんか」と僕以下の若手達が誘ってくれたので覗きに行ってみたら、皆でモノポリーをしていました。部屋の一カ所にモノポリーをしているメンバーがいて、他にTVゲームをしていたメンバーもいたのかな(笑)。
地方巡業に行けば、仲間達とご飯食べたり飲みに行ったりはします。けれど終わったら「じゃあね」とそれぞれ次の場所なり自分の部屋へ帰って行きます。琴平(ことひら:こんぴら歌舞伎が開催される金丸座がある町の名前)は何でも揃っているわけではないだけに、長い夜(終演時間は18時台)を過ごすうちに「じゃあひと部屋に集まって」となって、お酒を飲むでなく、芝居の話をするでもなく、ぐだぐだとゆったりとした交流を持つ、ということになるのです。それは琴平でなきゃ出来ないことでしょう。
その他「こんぴらならでは」というお楽しみをいくつかお話しください
(松也)
金丸座は江戸時代末期の木造建築ですから、現在の歌舞伎の劇場より遥かに小さめで、外から陽の光を取り込んだりと、独特の造りと雰囲気です。お客様と役者の距離がとても近く、一体感を強く感じますね。皆さん目をきらきらさせてご覧になっていらっしゃるのがわかります。今回牛車が登場しましたが、普通の歌舞伎の劇場用に作ってあるものを持って来たわけで、金丸座ではどうなるのか期待していました。寸法の違いのせいで牛車がより大きく見えて、楽しめるのでしょうね。「女殺油地獄」は一日の最後の演目で、上演中に段々外が暗くなって行きます。暗い劇場全体が舞台の大道具の一部になって行くような感じを与えていて、まさに金丸座でならでは!です。先日雨が降った日、「寺子屋」の首実検のところで、劇場全体がしーんと静かに張りつめた空気の中、雨音がもろに聞こえて、それがすごくリアルな感じがして、素敵だなあと感心しました。前回の出演の際は、海老蔵さんが「暫」をなさったのですが、すごい存在感というか、本当に昔っぽい感じが出ました。実際昔はこういう迫力だったのかな、とね。小さい劇場にああいう大道具とかああいう主人公を置くと、迫力が違うのですね。
前回の出演では、「角力場(すもうば)」という演し物(だしもの:自分が主役の演目)をさせてもらいました。本興行で演し物をするのは、全く初めてでした。それから6年の間にいろいろ経験を積んで、今回「加茂堤(かもづつみ)」という演し物をさせてもらって、非常に嬉しいです。こうして若手がチャレンジ出来るというのも「こんぴらならでは」です。若手役者にとって、ここは貴重な経験の場なのです。
こんぴら出演の機会は役者さん達に順繰りに与えられますから、次回が何年後になるかはわからないのですよね?
(松也)
そうしょっちゅうは来られません。けれどその分、「次回までに自分はどうなっていたいか」と意識しますね。前回は、「今は若手役者のひとりと思われているけれど、次回の出演までにはもう少し知られている存在になりたいな」と考えていました。前回と今回と続けて演し物をさせて頂いて、「次回も演し物をさせてもらえたらいいな」と思いますが、大きな事を言ってしまえば、「将来いつか座頭(ざがしら:トップ)としてここに来たいな」とも思います。
先輩の役者さんの中には、十何年来てないとか、全く来た事がない、という方もいらっしゃいます。本当にご縁次第なのです。僕も子役の時から前回までは間がかなりたっぷり開きましたし、今回も6年振りですから、次回がいつになるかわかりませんが、また来られる機会があると信じて、それを楽しみにして、精進して行こうと考えています。毎年温かく歓迎してくださる地元の皆さんに、「松也が戻って来るのが待ち遠しいな」と思って待っていて頂けたらありがたいですね!
こんぴら歌舞伎に対する松也さんの想いが、率直に伝わって来るインタビューでした。遠くない将来「今回のこんぴらでは・・・」とのお話しが聞ける事を、そして座頭の体験談を伺える事を、心待ちにしております。本日はありがとうございました。
4月8日琴平にて
「~知られざる物語~京都1200年の旅」出演二年目を終えての思いの丈を、たっぷりと述べて頂きます。
とても楽しげに散策なさる姿が印象的ですが、撮影スケジュールはきついそうですね
(松也)
歌舞伎に出演していると、丸々一日身体が空くというのはせいぜい月に一日程度です、千穐楽の終演後に東京駅から新幹線に乗って京都入りして、翌朝早くから撮影して、その晩のうちに帰京して、翌日から翌月のお芝居のお稽古という動きを繰り返しています。休みが無い場合でも、舞台出演が昼の部だけ夜の部だけであれば、二時間、三時間だけの撮影のために京都入りして東京に戻るという強行スケジュールも幾度かやりましたね。公演が大阪や京都の時も、時折その様な往復をします。なかなかハードです。けれど、昨年番組に坂東巳之助君が加わってくれてからは、随分と楽になりました。
朝一番の新幹線で京都着というわけにはいきませんか?
(松也)
残念ながら、そうはいかないのですね。訪問先が六ヶ所七カ所あるから、「日の出とともに」といった時間からスタートしないと一日で全部まわれないのです。寺社仏閣には特に配慮して、一般のお客様が拝観に来られる前になるべく撮影を済ませたいという考えもあり、必然的に撮影の開始時間が早くなります。
朝に弱い松也さんには過酷過ぎるスケジュール?
(松也)
決して早起きするのに好きではないけれど、それに値する良い経験良い勉強をさせて頂いて、心からありがたいと感じています。神社仏閣や仏像を見てまわる「見る」という行為も充実しますけれど、見るだけではなく、山登りや川下り、和菓子作りといった体験もさせて頂けて、受ける刺激はいくらもあります。
旅番組ですから、天候が気になりますね?
(松也)
ロケである以上、撮影が気象条件に左右されます。予想より早く外が暗くなって困ったとか、このシーンは雨が降る前に撮りたかったのに降り出してしまったとか、といった事がありました。日照時間は短いし、急に雪が降り出したりもするし、一番気がかりなのは冬場です。山の中の撮影も結構多いですが、山の天気はまた大変です。雲が厚いと撮影を止めて晴れ間が見えるまで待つ事もあります。お寺の中で待機していると、強~烈に寒いんですよ!板張りの床なんてがんがんに冷たい!靴下を何枚も重ねて履いていないと、足が凍傷を起こしてしまうのではないかって、勿論そんな事あるわけないですけど(笑)。
放送をご覧になって「ひとり反省会」はなさいますか?
(松也)
毎回緻密にではありませんけれど、放送を収録したディスクを見る事はします。番組を始めたばかりの頃は、眩しいとか暑いとか寒いとか、案外感情はっきり見せちゃっていました。それは見映えがよろしくありませんね。コメントのチェックはしっかりします。前任者(注・番組の「旅人」の前任者)の市川猿之助さんの様に神事や故事にすごく造詣が深くはなく、歴史の知識も歌舞伎役者として最低限レベルでしかない僕としては、自分の心に浮上した思いや疑問を素直に紹介しようと心がけています。撮影後にスタッフの方がきちんと僕のコメントを編集してくださるわけですが、まずは自分で視聴者の皆さんに共鳴して頂けるような発言をしよう、と気にかけているというわけです。
猿之助さんと一緒に収録をするという企画はなさそうですか?
(松也)
スタジオで撮影なさる猿之助さんと僕は別行動です。もともとは猿之助さんが「旅人」として活躍なさっていらして、お忙しいからもう一人必要という事で僕が参入させて頂いたので、一緒に京都をまわる事はありません。猿之助さんとお芝居でご一緒して、楽屋で「1200年の旅」の話で盛り上がるという事は勿論あります。
番組スタッフの皆さんについてお話しください
(松也)
スタッフの皆さんとは、一緒にロケバスで移動して神社仏閣をまわり、暑さ寒さに耐えながら山登りや川下りを経験して来た仲です。機材を担いでいる分、彼らは僕より遥かに大変ですね。僕の難しいスケジュールに合わせてくださり、時間を共に過ごして絆を築き上げられたのは、大変にありがたい事です。スタッフさんの多くは大阪を拠点にしていらっしゃるので、僕が公演で大阪に滞在の際は、ご飯をご一緒したりしてますよ。
このインタビューをお読みの皆様に、「松也のイチオシお勧めスポット」をご紹介ください
(松也)
行って良かったと思ったところは沢山ありますけれど、あえてお勧めスポットとしてあげるとすれば、比叡山とか鞍馬山とか、たどり着くのにつらい経験をするところですね。達成感があるのですね。「挑戦する」との心持ちで、こういった修行の地を体験なさるのは良い事だと思います。登り続けてたどり着いた比叡山の上は空気がものすごく澄んでいて、自然の音しか聴こえない、心が洗われるというのはこういう事なんだ!と実感した場所でした。ぜひお勧めしますね。でも僕みたいにスーツに革靴で行かない方がいいかなあ(苦笑)。
昨年の今頃行った「一年目終了」のインタビューでもそうでしたが、今回のこのインタビューでも、番組に対する松也さんの情熱や愛着といった熱い思いがひしひしと伝わって参りました。これからも、より楽しく旅をお続けください。本日はありがとうございました。
3月12日 京都南座にて
毎年一月恒例の、「前年を振り返る」というお題で語って頂きます。
2013年は、極めて多種多様なお役に挑戦する年でした
(松也)
何よりまずは一月の「曽我対面(そがのたいめん)」の曽我五郎(そがのごろう)が非常に印象に残っています。荒事(あらごと:歌舞伎の伝統的な演出のひとつで、男性の主人公が荒々しく動き喋る)とは全く無縁でいましたので、いきなり予想もしていなかった荒事のお役を頂戴したのは驚きでした。主役を与えられた喜びと、「自分の五郎でいいのか」「自分につとまるのか」との不安が混ざった、衝撃的な経験でした。一ヶ月やってみてまだまだわからない事だらけでしたが、身体をダイナミックに使って力強く見せるには、実は繊細な計算が隠れていたりしていて、格好良い荒事が出来るようになるまでにはかなりの道のりがあると痛感しました。
スペイン人にもイタリア人にもなられました
(松也)
イタリア人(「ロミオ&ジュリエット」のベンヴォーリオ役)はミュージカルですから、覚悟の上でしたが、「GOEMON」のカルデロン神父は歌舞伎の中で演ずるスペイン人で、これまた驚きの、インパクトの有るお役でした。初演では歌舞伎の出身ではない方がカルデロン神父役をなさったので、再演のこの時は楽しみながら自分なりのスペイン人を作らせて頂きました。フラメンコを踊るというのはかなり大きなチャレンジでしたね。フラメンコの稽古期間は一週間あったかなかったかという具合で、それは大変でした。初演でのフラメンコ経験者も居た中、なるべく引けを取らないよう頑張らねばという心境でした。でも楽しかったですよ(笑)。
初の大悪人経験のご感想は?
(松也)
「女清玄(おんなせいげん)」の猿島惣太(さるしまそうだ)は大敵(おおがたき:悪人中の悪人といった役柄)という、これまた全く新しく、刺激的なお役でした。荒事同様、大敵もそれまで意識していなかったジャンルでしたけれど、「やってみたい」という願望は実はもともとあって、頂戴してとても嬉しかったですね。「女清玄」はご縁のなかった演目でしたので、映像などの資料をもとに予習して役作りをしました。福助さん・錦之助さん・翫雀さんといった先輩方が「自由に演じてごらん」と言ってくださって、皆さんが僕の演技に合わせてくださって、自由な発想で工夫をしながら、毎日本当に楽しくて仕方ないという舞台でした。悪を演じるって、もしかしたらストレス発散という効果もあるのかなあ・・・・悪を演じるのはすごく気持ち良かったですね(笑)。
「これからいくらもワルやります!」でしょうか?
(松也)
そうですね、「ワルやりたい!」ですね(笑)。
一年間、全く女形のお役がありませんでした
(松也)
「女形が観たい」という声は多々頂きました。勿論やりたくないわけではないのですが、お役ばかりは僕が決められるわけではないのでね。女形の悪もやってみたいです。女形をするとしても、これからはお姫様や楚々とした娘といったお役が来るとも思えませんから、女形の悪役もいつかぜひ。
昨年は歌舞伎座というホームスタジアムの開場という、特別な年でもありました
(松也)
役者達の中でも、「やっと開場!」という期待が高まっていましたね。実際開場すると、あっという間に歌舞伎座があるのが当たり前となって、三年の間歌舞伎座無しで過ごしていたという過去はさっさと忘れてしまいました(笑)。やはり歌舞伎座があるという事は、役者達にとって心強い事です。
昨年一月のこのインタビュー欄で、「固定観念にとらわれない一年にしたい」といった発言なさいましたが、実際はいかがでしたか?
(松也)
その発言をした時点では既に曽我五郎を演じていて、その後歌舞伎でどのような役を頂けるかもミュージカルに出演するとも、ある程度わかっていました。ですからその発言は自分に対する言い聞かせであった気がします。「柔軟な考えで臨まなければ達成出来ないぞ」との言い聞かせですね。本業だけに限っても、荒事や大敵に初めて挑むのですから、それまで自分が培ったものを一旦横に置いて、改めて新鮮な気持ちで挑戦する、という決意をあえて言葉にしたという事だと。
「何事にも固執せず、頭を柔らかく」と意識し続けながら歌舞伎にミュージカルに挑んだ結果、ふとした瞬間、自分の中の引き出しが勝手に引き出て来てくれたと気づく事が時折あって、「少しは結果を出せたかも」と嬉しくなりました。
「今年は○○○したい」との目標をあげてください
(松也)
(しばし考え込んで)そうですねえ・・・・忘れ物かなあ、忘れ物を減らしたいかな・・・・忘れ物が結構多いので、最近はなるべくチェックしているのですけれどやはり多くて・・・・今年は「仕事もプライベートも忘れ物をしない!」という目標をあげましょう。
最後に一言ファンの皆様にお願いします
(松也)
今後もいろいろチャレンジして行きたいと願う一方、歌舞伎役者としての誇りを大切にし、古典をきちっと勉強しようと心しております。これからも変わらずの応援をお願い申し上げます。
多方面に渡っての益々のご活躍を楽しみにしております。本日はありがとうございました。
1月9日 国立劇場楽屋にて
歌舞伎座では先月今月と二ヶ月に渡り「仮名手本忠臣蔵」が昼夜で上演されていますので、今回は忠臣蔵を巡ってのお話をいろいろお伺いいたします。
「仮名手本忠臣蔵」はとても人気の高い演目ですね
(松也)
ご存知の通り、この物語はもともと江戸城内松の廊下での刃傷沙汰という実際の事件がもとになっていて、それに歌舞伎独特のアレンジが加えられている作品です。関係者達がどんな苦労をして討ち入りに至るかの経緯に、ところどころにフィクションを交えての大変長い演目(注・物語は十一段に分かれている)なのですが、お客様にはぜひ昼の部夜の部と通して観て頂きたいですね。歌舞伎では「五・六段目」だけ、「七段目」だけといった、切り離しての上演も良くありますけれど、やはり通しで、事件の発端からお殿様の切腹そして討ち入りとすべて順を追って最後までという方が、お客様も役者達も気持ちが高まりますからね。
上演頻度が高い作品なのに、今回で三度目のご出演だそうです
(松也)
十代後半に、大星力弥(おおぼしりきや:実在の大石主税にあたる)役で初めて出演いたしました。その後諸士(赤穂浪士)で出演するのであろうと想像していたのになぜかご縁がなく、昨年四月に顔世御前(かおよごぜん)という、塩谷判官(えんやはんがん:浅野内匠頭にあたる)の奥方をやって、そして今回竹森喜多八(たけのもりきたはち)という諸士のお役を頂戴しました。
あの定番の黒と白の討ち入りの衣装は、今月初めてお召しになったのですね?
(松也)
力弥をさせて頂いた時に討ち入りに参加しましたけれど、力弥は他の諸士達とは装束が違いますから、今回初めてあの衣装を着ました。
今回のお役を告げられた時の反応は?
(松也)
力弥をやらせて頂いた時から、「竹森喜多八は格好良いな、やってみたいな」と憧れていましたから、喜多八と知らされて非常に嬉しかったですね。この前は顔世御前という女形の大きなお役をさせて頂き、そして今回は憧れの竹森喜多八をやらせて頂くというのは贅沢だなあという気がします(笑)。
竹森は十一段目の討ち入りの場面で「泉水(せんすい)の立ち回り」と呼ばれる大立ち回りを見せます。小林平八郎という剣豪と二人だけで戦って小林を討ち取るという、一度でも「十一段目」をご覧になった方なら絶対に記憶なさっていらっしゃるという名場面です。大雪の中で戦って池の中に落ちるという(後に無事這い上がる)派手なアクションをお見せする、とても格好良い役なのです。でもかなり体力的にきついですね。見るとやるとは大違いと言いますけれど、ホント、楽しいですけれどきついです(苦笑)。
前回経験なさった顔世御前についてお話しください
(松也)
今月七之助君が演じているのを見ていると、自分がやった時の事を思い出します。ノーマークだった顔世はとにかく教えて頂いた通りを忠実に演じようというだけでしたけれど、やりがいのあるお役でしたし、機会を頂戴出来ればもう一度トライしてみたいとの思いは強いですね。最近僕は立役(男性の役)ばかりで女形は減ってしましたけれど、決して女形が嫌いなのではありません。どのお役であっても、他の方がなさっているのを見ると「ああ、こういうやり方もあるのか」「自分だったら、こうこうこうやってみたいな」といった思いを抱くものです。経験した事のあるお役であれば、経験したからこそ、より深く考える楽しみがあります。
演じてみたいお役はいくつもおありだそうですね?
(松也)
主役級も諸士も魅力的な役どころがいっぱいあるのが「仮名手本忠臣蔵」ですから、やりたいお役は沢山ありますね。女形を多く勉強していた頃はお軽がやりたかったし、立役が多い最近では若狭之助とか平右衛門とか、高師直(こうのもろのお:吉良上野介にあたる)は面白いだろうなと思います。もしやらせて頂けるとしても、遥か先の話でしょうけれどね。師直も塩谷判官も斧定九郎も早野勘平もやってみたいですね。おかげさまで今僕は幅広くいろいろな役をやらせて頂いていますから、「忠臣蔵」のあらゆるお役に挑戦出来たらいいな、と思います。
映画「尾上松也ひとりで忠臣蔵全役」という企画はいかがでしょうか?
(松也)
やってみたいですね、遊びでね、面白いかもしれません(笑)。
史実について個人的な意見をご紹介ください
(松也)
吉良は実は親切な人でただ注意しただけなのに浅野が短気を起こしたとか、この事件についてはいろいろ憶測がありますね。江戸時代中期という平穏な時代において、討ち入りは本当に主君のためなのか、自分達の大義名分のためなのかというのも分からないところであり、幕府としても、事前に討ち入りに関して全く知らなかったのかというと定かではないですよね。沢山の思惑やもくろみがあって、それらがどういうところでどう交錯していたのかはわかりませんけれど、浅野の家来であれば、主君の一時の感情の爆発で家来全員が職を失ったわけですから、「主君としてそれはあんまり」と恨んでいたのかもしれません。討ち入りの参加者が四十七人になったのは、結構な数が参加しなかったという結果ですからね。家来全員が一致団結していれば、遥かに上回る数になったでしょう。考えてみれば、四十七という数は複雑ですよね。とはいえ、実際の浪士達の苦労を想像するに、あらゆる困難に耐え抜いて討ち入りを果たしたとは頭が下がる思いです。
憧れのお役の数々を語る時は熱っぽく、史実についての思いはクールにと、がらりと気持ちを切り替えられてのインタビューでした。本日はありがとうございました。
12月10日 歌舞伎座楽屋にて